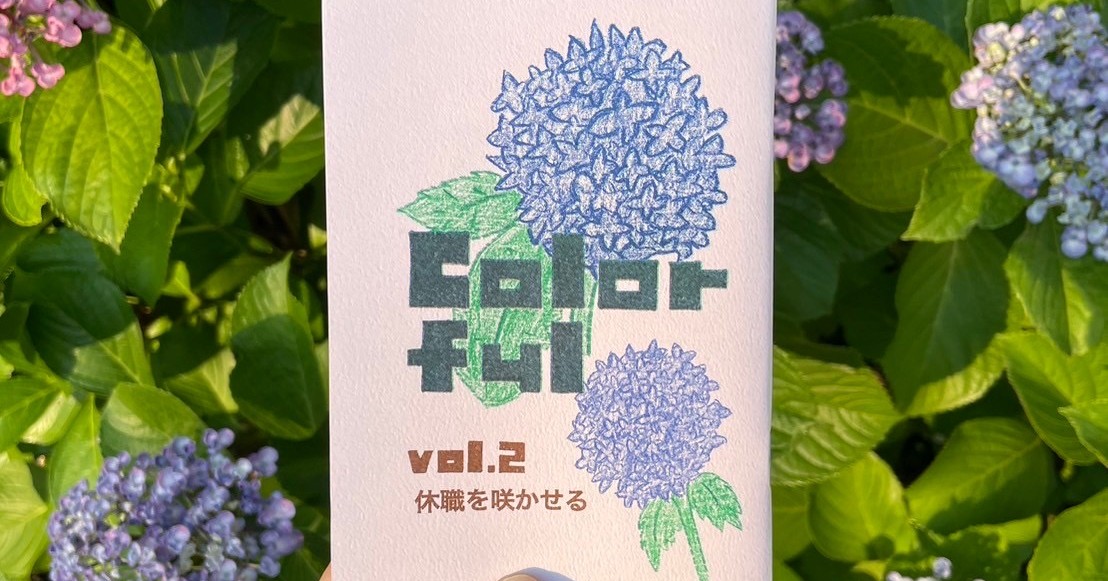二人読書会 vol.1『ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義』(大和書房)
私たちは、イスラエル国家による植民地主義、民族浄化、ジェノサイドに強く反対し、パレスチナに連帯します。
これまでパレスチナで起きていることに対して長らく関心を向けられていなかった私たちが、書籍『ガザとは何か』を読み、感じたことや今の想いを二人で話しました。今回のニュースレターは、そのときの会話をテキストにしたものです。
実はこの収録からはすでに1ヶ月半もの時間が経ってしまっていて、ここまで自分たちはやるべきことをできただろうか?という反省や、この会話を配信することよりも他にもっとやるべきことがあるのではないかという葛藤や罪悪感が、これを書いている今もあります。
けれど、たった一人だけでもいいから私たちがこうして書いたことが届き、起きていることに対して目を向け始める。そんな小さくとも大事な変化がどこかで起きることを願って、これを配信するに至りました。
(読んでいただくにあたって:事態が常に変わっているので、内容は2024年2月当時の情報になります。また私たちも勉強中なので、きっと間違いや曖昧な情報も多数あると思います。明らかな間違いがあれば訂正したいと思いますので、何かお気づきの点があればぜひコメントください。感想やシェアも大歓迎です)
---------------------------------------------------------
2月3日(土)快晴
M:この読書会は、何を目的としようか?
S:うーん、この本を読んでない人、または読む時間がない人、パレスチナで起きていることを知らない人のために何か....
M:読むきっかけになるような、とかかな?
S:そうだね、読むきっかけになったらいいかな。それか、仮に読むことができなくても、これを見てもらえれば何か分かるような...(いや、でもそれは難しいか...)。
この先々で何かパレスチナに関することを読んだり知ったりしたときに、私たちの話していたことを思い出してもらえたり、ヒントになれたり。とにかく何か残ることがあればいいな。
この本と、そして起点となったセミナーのこと
S:まずはこの本の内容について簡単に。『ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義』は大和書房から出版されました。去年の12月31日に発行されたんだね。
M:本に収録されてるセミナー自体は去年の10月に開催されたものだけど、出版されたのは本当に最近なんだね。
S:この本には、10月に京都大学と早稲田大学で開催されたガザに関するセミナーで登壇者の岡真理さん(※)が実際に話したことが収録されていて、一本目が10/20に京都大学で開催された『緊急学習会 ガザとは何か』というセミナー、二本目が10/23に早稲田大学で開催された『ガザを知る緊急セミナー 人間の恥としての』という題。
※プロフィール:早稲田大学文学学術院教授。専攻は現代アラブ文学・第三世界フェミニズム思想(2023年12月時点・大和書房ホームページより抜粋)
M:本の「はじめに」にはこの本が出版されたきっかけも書いてあったよね。
S:大和書房の編集者の方から「この二つの講演内容を本にして緊急出版したい」ってセミナーの三日後に連絡があったって書いてあったね。この講演自体も、市民の有志の方々が企画して岡先生に登壇を依頼したんだよね。
M:早稲田大学で開催されたセミナーは、主に学生さんによる企画なんだよね。
S:そうそう、京都大学は市民有志の方々で、早稲田大学は10月16日のイスラエル大使館前でのデモで出会った方々、<パレスチナを生きる人々を想う若者・有志の会>による企画とあったね。スピード感がすごいよね。
私たちが目を向けていなかったここ数ヶ月のこと
S:ちなみに私個人の話をすると、この緊急セミナーが開催されることが決まった10月当初、お店や友人・知人のSNSを通してこのセミナー開催の告知画像を目にするようになって。けれど、正直に言ってしまうとつい最近までパレスチナのことは自分と全く関係ないこととして生きてしまってて、そのときはスルーしてしまったんだよね...。充はどう?
M:うん、自分も同じだね。僕は『ガザとは何か』は紗弥加が読んでたから読んだけど、学生たちがこういう発信や活動をしているのに、29歳にもなる自分がこの問題に全く関心を持っていなかったことが、自分がかつて漠然となりたくないと思ってたような視野の狭いダサい大人になっちゃってたなって思って、本当に反省してる。学生たちがこうやって行動に移してて、その一方での自分の無知さと愚かさというか。「うわ、企画したのは学生さんなんだ」って、本を読みながら一番に思ったのはそこだったかな...。
難しそうと思っている人へ
S:私が『ガザとは何か』を読もうと思ったきっかけは、SNSでフォローしてる書店が年明け頃からこの本を入荷情報としてアップしているのをたびたび見かけるようになって。シェアしてる友人もいたから気になってたんだよね。それでよく見たら「去年の10月に何度も告知画像を見かけた、あの岡真理さんのセミナーじゃん」って自分の中でようやく繋がって。実際にセミナーも聞けてなかったし、パレスチナのことに一切向き合えてなかったことにずっと罪悪感はあって。テキストだったら読めるかも、読みたいなと思って、それで西荻窪の今野書店に行く機会があったときに買った。私は買ってすぐに2回読んで、そのあとに充も読み始めたね。
M:うん、二日で読んだ。すぐ読めたよ。実際に講義形式で話したことが収録されてるから、みんなに開かれた言葉っていうのかな。とにかく分かりやすかった。
S:話し言葉だし、読みやすいよね。構成として、文中で見出しがこまめに出てくるのも分かりやすいなって私は思った。そもそも内容自体が分からないことだし、読んでて知らない言葉が続くと、どんなに一生懸命に読み進めてもどうしても頭が追いつかなくて止まっちゃったりするものだと思うけど、これは図や写真があったり大事な部分が太字になってたりして、難しくないって思わせてくれる一冊だった。
みんなが問題の当事者だって思うから、本当は学生時代の専攻とか、文系か理系かみたいな話ってここでは関係ないけど....それでも私たちはどちらも、選択科目としては世界史は勉強してないよね?私は日本史だったんだけど、充は数学だよね。
M:うん、世界史は必須科目のうちはやったけど、学生時代はテストの点数を取るためだけの勉強だったかな。
S:私もそう...。今は歴史を学ぶことはすごく大事だと思うけれど、勉強が好きじゃなかった学生時代は「歴史を勉強する意味ってなんだろう」とかって思っちゃってたんだよね。本当に”机の上での勉強”でしかなくて、勉強することの本当の意味が分かってなかった。でもそんな私たちでも読めた。だから難しそうって思う人にこそ本当に読んでほしい。
M:まず、難しくないと思うけどね。
S:うん、難しくない。けど「難しそう」って感じちゃう人の気持ちもすごくわかるんだよね。
私がそうだったんだけど、何も知らないと、誰が当事者で、誰が対立していて、何が起きていて、どっちが悪くて、みたいな分かりやすい答えを求めてネットに調べにいく。でも基礎知識からシンプルに教えてくれる情報にはなかなか辿り着けない。それでせっかく何かを読み始めたりしても、「うーん、難しいし、ちょっと分からないな〜」ってくじけるっていう。少なくとも私はそれが続いてて、それがこの本を読んだおかけでようやく筋立って理解できた。
情報の取り入れかたって色々あって、図で見る、絵で見る、動画で見る、SNSの発信で、とか人によって入ってきやすさはそれぞれだと思うけれど、本は自分のペースで読めるしすごくいいと思うな。それにこの本には、セミナーを企画・開催した有志の人たち、講義をされた岡真理さん、出版のために動いた編集者の方、そして意思を持って仕入れて販売している本屋さん、色んな人たちの想いが詰まってるって感じる。
本の内容の紹介 - 第一部
M:最初に年表が付いてるのもいいよね。本を読みながらネットに戻って調べるってことがなかった。何かあれば本についている地図や年表に戻れるから、読んでて集中が途切れなかった。
S:そうだね。ちなみにこの本の第一部の見出しはこんな感じ。
・今起きていることの4つの要点
・封鎖されているガザで何が繰り返されているのか
・ガザとはそもそも何か
・イスラエルはどのように建国されたのか
・ハマースの誕生
・出身者のスピーチ
S:一連の報道で「ハマース」という言葉を聞いたことない人はきっといないよね?テレビやネットニュースの見出しでも見ると思うし。
M:ハマースよりも、やっぱり「イスラエル」という言葉のほうがよく聞くんじゃないかな?
S:そうなのかな?でも「ハマースが侵攻し、それに対してイスラエルが反撃して衝突」みたいなメディアがよく使う文脈は、きっと多かれ少なかれ耳にしてるよね。
本の内容の紹介 - 第二部
S:第二部は別日に開催されたセミナーなんだけれど、そのあいだもガザで侵攻が進んでいるから、岡真理さん自身もつらいという気持ちをそのまま話していて。第一部のおさらいができるし、生身の人間として大事なことを第一部よりもさらに強く投げかけている感じがして、一部も二部もそれぞれに大切な内容だなって思った。第二部の見出しはこんな感じ。
・ガザ、人間の恥としての
・問うべきは、イスラエルとは何か
・これは人道的問題ではなく、政治的問題
・セミナーにきている人たちの質疑応答
・もっと知るためのドキュメントガイド(映画、ドキュメンタリー、本、情報サイト)
M:ネットとかで見かけて点で気になったことを調べても、全貌が見えないから結局よく分かんないまま終わることってあると思うんだよね。この本だと全部繋がってて時系列で分かるから、本当は誰が誰のために戦ってて、何が背景になってこのような侵攻やガザの封鎖が起こっているのかっていうことが理解できると思う。
起きていることを知った今、自分たちが思うこと
S:この本を読んで、そして昨日初めてデモに参加して共通して思うのは、やっぱり「知ろうとすること」の大切さかな。
この問題の歴史を遡るとユダヤ人のホロコーストが一つキーになるわけで、ユダヤ人が迫害された歴史自体は私たちも学校の授業で学んだよね。生き残ったユダヤ人のための国家としてイスラエルが建国され、そのためにパレスチナの人々が追放・迫害された。ホロコーストは悲劇で絶対にあってはいけないことだったけれど、結局はそれが他の人種や民族に押し付けられた。これってたぶんちゃんと知ろうとしないと知れないことで(学校で習っても、私みたいに記憶に残ってない人もたくさんいるだろうし...)、私たちは今回たまたま本から学ぶということに辿り着けたけど、時間がないとなかなかそうならないと思うんだよね。
昨日行った外務省前でのデモも、本当に何も知らないと、なぜここに人が何人も立って話しているのかってピンとこないと思うんだよね。絶対に目を合わせないぞって思ってるんだろうなって感じで早足で下を向いて通り過ぎて行っちゃう人が何人もいたし、逆にこっちを見て、何を語っているのか知ろうとしている人もいた感じがしたな。自分もついこの間までそちら側だったし、それもすごく分かるんだよね。なんか本当に色々感じたな。
M:自分はパレスチナの本に関してはまだこの一冊しか読んでないからこれからも読みたいし、『ガザとは何か』の最後についてた参考図書とかも読んでいきたいと思ってる。
ただ一つ思いたいのは、本をたくさん読んだから発言できるとか、逆にあの人はちょっとしか読んでないからあまり知らないだろうなって思う、みたいになっちゃうのは気をつけたほうがいいなっていうこと。その視点は忘れずに自分の中に持っておきたいと思ってる。
本当に大切なことを見失わない
M:知識量や勉強量のことを言い始めると色んな人の発言を妨げになっちゃう気がして、世の中で言う「論破」みたいな感じというか。誰かに何か言われたときにうまく反論できないかもって考え始めちゃったり、そういうのはよくないなと思うんだよね。
たとえ反論がうまくできなくてもそれはそれでいいし、自分が本を読んで何をどう感じたか、それでどういうアクションを起こしたのかが一番大事なのかなって。それに対して人が何かを言ってきたり、自分の分からないことにぶつかったら、またそのとき学べばいいと思うから、自分に今ある情報で語ることが大事なのかなって思う。
昨日のデモも自分は初参加で、きっと他の人のほうが知識量もパレスチナのことに掛けてきた日数も違うと思うけど、でもデモの場合はそこにいることと数が大事だから、そこは対等な気持ちで参加したいって思ったかな。
S:それは結構大切なことかもね。パレスチナの問題に関してもそうだし、それ以外のテーマも何にでも当てはまることだと思うな。どっちのほうが詳しいっていう競い合いになってくると、物事の本質とずれてきちゃうしね。
M:もちろん何かを言ったり書いたりするうえで間違えないように慎重になるのは大切だけれど、仮にそれが間違ってしまっていたら「間違ってた」とちゃんと後で訂正すればいいし、間違えることを恐れて何も言わないことが一番、イスラエルのやってることを許してしまうことに繋がるって思う。
S:そうだね。間違いって意味では、抑圧されてる側や犠牲者をさらに傷つけてしまうという事態だけは本当に気をつけたいと思うけれど、間違えることを恐れて黙ってしまうことはないようにしたいな。
もしも自分たちの身に同じことが起きていたら
M:今大事にしたいと思うのは、「これっておかしいんじゃないかな」と思うことをできるだけ自分ごととして想像してみることかな。
もし自分が今ガザにいてそこに家族や友人がいたら、って想像することは大事だと思うし、そうやって想像してみると離れた安全な場所にいるからこそできることってあるなって気づくというか。少なくとも僕の場合は、仮に自分が今ガザにいたとしたら怖くて声をあげられないんじゃないかと思ってしまう。殺されたくないから。けれど今自分は安全な日本にいて、だからこそできることがあると思うし、それをやるのは大切だなって。
あとデモに行ってみて思うのは、SNSのバーチャルな世界とは違って、その場に行くと自分と同じ方向を向いている人たちがいるんだなってフィジカルで確認できたのがよかった。デモをやっていても知らんぷりして通り過ぎてしまう人がいたときに生まれた感情や悔しさも、別の国から来ていそうだなと思う人がデモに参加してて横で声を上げていたことで感じたことも、その場に行ったからこそ体感できたことだなと思う。
それからこれは個人的な体験に紐づくものになるけれど、昨日のデモの場には他国出身と思われる人も何人もいて、一緒に並んで声を上げて、なんだか自分の留学のことを思い出した。言語の壁はあったとしても、何かに対して声を上げるために集ったときに、日本にもこうやって同じように声を上げる人がいるんだなって思ってほしいし、日本にいてよかったなという気持ちも持ってほしいなって。そういう意味でも、やっぱり自分は連帯を示すためにできるだけ積極的にそういう場に足を運びたいなと思った。
S:私たちが知らないだけで日本が加担していることって本当にたくさんあると思うから、パレスチナ出身の人とかを前にすると合わせる顔がないみたいな気持ちにもなってしまうんだけれど、だからこそ自分が足を運ぶことができる限りはその場に行くようにしたいよね。
昨日はスタンディングだったし、スピーチとかもなかったから来ている人のプロフィールは分からなかったけれど、自分たちは今時間もあって、体力もあってという時期にいるわけで、本当に数が大事だからできる限りデモには行くようにしたいね。充が言ったように、これまで学んだ量は関係ない。昨日のデモは、本当によく分からずとりあえず手ぶらで来たみたいなところもあったけど、いざあの場に立ったら関係ないなと思った。
どんな問題においても当事者が声を上げることって本当に大変なことだと思うから、何かを知ったとき、声を上げられる立場にいるのなら上げないとなあって思う。さっきのダサい大人の話にも戻るけど、少なくとも自分はそうありたいなあって。もちろんやれてないこともたくさんあるし、時期によってやれるときやれないときもあると思うけれど、細く長く続けたいって思う。
この世界の状態を当たり前だと思いたくない
S:ふと冷静になったときにおかしいよなと思うのは、私たちが生まれた頃、なんならもっと前から、世界のあちこちで紛争とかが起きているのがデフォルトになってること。
日本も歴史を振り返れば戦争があるし、なんなら今だって危うい兆候がたくさんあるから遠い話ではないなって恐ろしく思っている自分もいるけれど、けど今はたぶん平和ではあって。パレスチナをはじめとして紛争が起きている地域の人たちも、こうやって日本で生きる私たちと何ら変わりなくみんな生身の人間で、自分の暮らしがあり、大事な人たちや家族がいたりして、それぞれの人生を生きている。それなのに、「あの地域はずっと紛争があって、人もたくさん亡くなってるんだよね」みたいなのが当たり前になってるのって普通に考えておかしい。
人が殺されちゃう日常があるなんて、本当はあっちゃいけないこと。だからそれに慣れちゃうんじゃなくて、あれ、これってなんで起きているんだっけ?っていつも問いかけていきたいって思う。そんな状況を自分ごととして想像するのはもちろんつらいけれど、これってどこに生まれ落ちたかの違いだけだなって思うから、全然他人事じゃない。だから想像することをやめたくないし、知ろうとする、調べるっていう動きを広めていきたいって思う。想像してみることって、知識とかがなくたって誰でもすぐにできると思うから。
デモで言ってたことだって、当たり前のことでしかない。「自由」「殺すな」「封鎖するな」「占領するな」って、本当に全部当たり前で、なんでこれを言ってるんだろう?ってなる。少なくとも自分には今このどの権利も当たり前に守られてるって感じるけれど、それがない状況、わざわざ言わなきゃいけない状況っておかしいよなって。
誰がそれを言っているのか
S:これは私たちも本を読んで学んだことだけれど、「誰が言っているのか」っていうのはすごく大事な観点なんだなって。パレスチナのことに関しては、どの国がそれを言っているのかっていうのもあるし、あとはメディアにも言えること。
昨日、デモでよく聞く、”From River to the Sea, Palestine will be free(川から海まで パレスチナに自由を)” という言葉は、実際に地図で当てはめるとどういうことになるんだろうねって私たちが話してて、それで充が調べてて辿り着いたYouTubeの主張が、「じゃあユダヤ人はどこに行けばいいんだ?」だったんだよね。
M:そう。「"From River to the Sea, Palestine will be free" っていう言葉は、反ユダヤ主義的な考え方で、結局は暴力的である」みたいな感じだった...。
S:で、その放映をしているのがAmerican Jewish Comeittee(直訳:アメリカユダヤ人委員会)だったんだよね。(もちろんアメリカにいるユダヤ人にもイスラエルのやっていることに対して声を上げている人はたくさんいて、皆んながこのCommeitteeのような主張ではないけれど)私はその動画を見たとき、「誰が言っているのか」を見るべき代表例だったのかなって感じた。まあこれに関しては私たちも勉強中だし、答えは持ってないのが正直なところだけど....
M:というか、それぞれに自分の「正解」があるだけだから。
S:そうだね、自分の信じたいことを信じるものだよね。
昨日見つけたこの動画に対して私たちが話してたのは、イスラエル国家が75年以上前からやってきたことを棚に上げて「パレスチナの人たちのせいで自分たち(ユダヤ/イスラエルのシオニストの人たち)の居場所がなくなっちゃう」っていう主張って、だからといって占領や植民地化を続けていいことは全く正当化されないよねって。「じゃあ自分たちはどこにいけばいいんだ」っていう主張って、歴史を見るとなおさら論点がずらされてるって思う。でも本にもあったように、もし本当にイスラエルの教育から事実が消されていたとしたら、そういう文脈や会話ってイスラエル国内でたくさんあるんだろうなって感じちゃった。
M:本に書いてあったことだけれど、イスラエルでは本当の情報が国の中で制限されてたり、フェイクニュースが流布されてるってあったよね。まあ「何が本当なのか」っていうのはあると思うけれど、そうなると自分たちが昨日見たような動画を見たときに、「パレスチナの人やハマスは自分たちを脅かす存在だ」って信じる人ってイスラエルの中にはたくさんいるんだと思うんだよね。そこが怖いところだなって思う。
日本もそうかもしれないけれど、結局メディアが情報を選択して紡いで放送して、それを市民がテレビをつけて見て、情報を受動的に受け取る。でもその情報は、あくまでメディアにいる人たちが選んだもの。だから本当に何が正しいかを知るには、テレビ以外にも他の情報ソースにあたって、包括的に自分で見極めるしかない。
日本ではまだそういうことができて大丈夫だと思えるけれど、イスラエルみたいに国家レベルで情報の制限とかってなってくると、本当のことを知ることがどんどん難しくなっていくんだろうなって。そういう状況だと、歴史や事実と本当は違うことであっても自分の中に入ってきたことを「正」として受けとって、自分の中にある正義のために行動を起こしてしまうから、めちゃくちゃなことになる。
S:そうだね...。でもすでに何かを強く信じている人を変えるって難しいと思っちゃう。だから、それ以外の人たちで声をあげて束になるしかないのかな。
M:それもそうだし、そういう人たちが何かのタイミングで、「あれ、本当は違うのかも?」って立ち止まるタイミングがくればいいんじゃないかな。
自分たちが立つべき場所
M:つい話が大きくなりすぎて、「事実と異なることを信じちゃってる人の気持ちをどうやって変えられるだろうか」みたいな頭になっちゃうんだけど、シンプルに自分たちが誰の側につくのか、ということを考えればいいんじゃないかなとも思う。なんでその人たちの意見が変わらないんだろうっていうほうを考え出すとしんどい気もするし、ただ自分たちが連帯したい人たちの側について、簡単なことからやるしかないんじゃないかなって。
S:自分たちのメンタルを守るためにもそれは大事だよね...。私はつい「いや、でもさ...」みたいに揚げ足とってくる人とか論破しようとしてくる人の登場を想像してしまって。自分とは意見や価値観が異なる人から言葉で攻撃される可能性を心配して、言い返せるように準備しとかなきゃ、備えとかなきゃみたいな頭になっちゃうんだよね...。
それも大事な気はしつつも、でもそのコミュニケーションで自分がへとへとになっちゃうくらいだったら、充が今言ったように自分の限りあるエネルギーを自分が立ちたい側に立つことに使ったほうがいいよなとも思う。
伊藤忠商事とBDS運動のこと
S:自分たちの使っているお金がどこに流れているかってあまり考えないと思うけれど、自分が望まぬ方法で使われている可能性があるってことも学んだね。BDSという運動があって、たとえばイスラエルにお金を支援している企業をボイコットしようとか。このボイコットリストには、分かりやすいところだとマクドナルドとかが入ってる。
あとは伊藤忠(※)のことも知ってほしいな。自分もそれなりに大きい企業にいたから余計身近に思うけれど、自分がやっている仕事がまさか人殺しに繋がっているなんて思いもしないし、絶対に嫌だと思うけれど、軍事産業で稼いでいる企業って思っている以上にたくさんあるんだろうね...。
(※:伊藤忠商事の100%子会社である伊藤忠アビエーションは、2023年3月にイスラエルの最大手の軍需企業であるエルビット・システムズという企業と協力覚書を結んでおり、市民からは、イスラエルによる虐殺に参加しているのと同じだと強い抗議の声があがっていた。その後、市民たちの署名運動によって、伊藤忠商事は子会社とエルビット・システムズとの協力覚書を2024年2月中に終了すると発表した。尚、伊藤忠商事自身は、国際司法裁判所(ICJ)の暫定措置命令を受けてこの締結終了を決定したのだと述べている)
あとはパレスチナのこと以外でいうと、オリンピックのこととか、宮下公園、外苑の銀杏並木の伐採の件とか、有名で大手で外から見たら印象がいい企業だけれど、実際やってることは...みたいな話って、言い出すとたくさんあるね。ちょっと話がどんどん膨らんで、難しい方向にいっちゃうかな...
M:まあ、詰め込みすぎると大変ではあるよ。全部やろうとしないのも大事な気がする。
S:「詰め込みすぎると大変だ」っていうのって、自分たちが今遠く離れた場所にいて、苦しくないから言えることだなって思ってしまう...。でも限られた時間だからこそ効果があることに絞って、自分が消耗しないようにするっていうのは大事かもしれないね。
BDSの話でいうと、お金を悪しき方にまわさない、みたいなことって一番インパクトがあるし、何かを決める力がある場所や人に向かって意見を言うのは、その一つかなと思う。気候危機の運動とかもそうだよね。私たちが一生懸命エコバッグを使ったりゴミを減らそうとしても、実はそんなに温室効果ガスの排出量って減らなくて、しかもその横で石炭火力から大量に温室効果ガスが出てますよね?みたいな話ってあるじゃない。私たちがこんなに必死にやらなくても大きい部分をカットすれば早いっていう。大きいところへの働きかけは自分もなかなかやれてないから、自戒の念もこめてだけれど...。
でも疲れちゃわないようにするっていうのは大事だよね。デモに行くことも海外ではもっと日常にあるわけだし、自分ももっと身近にしていきたいって思う。
声をあげる
S:こうやって話してみると、喋るって難しいね。私ばかり喋りすぎたし...。それに、何かに対して声をあげるってことがなかなか浸透してないと思うし、自分たちもこういう場所で生まれ育ってきてるから慣れてないよね。怖さもある。
でも今、自分が誰のために声をあげたいかって考えたときに、自分よりも小さな子供たち、未来のためって思うから、だからどんなに小さくても声はあげていきたいって思うかな。
M:個人的には、でかく捉えすぎないのも大事かなって思う。自分の身近なことに当てはめて考えたらいいんじゃないかなって。「世界平和が」とか「戦争」って、考えるのは大事だけど、そう言うと規模が大きいから、なんというか言葉にするのは難しいけれど、もっと近くていいんだよなって思う。
たとえばパレスチナ連帯のポスターを印刷して、家のトイレに貼る。自分の意思を示す。そうするとトイレが気持ちのいい場所になるし、自分としてもいいなって思える。ちっぽけかもしれないけれど、まずはそういうアクションでいいような気もするんだよね。あまりあれもこれもってなると、宿題が増えちゃって大変だと思うんだよね。
S:そうだね...。うーん、けどずっと先頭に立って動いて声をあげてる人たちをSNSや署名運動で見てるから、私はそれは言えないんだよなあ...(泣)
でも、確かに入り口としてはそういう姿勢って大事だと思う。だし、それでいいのかも。そう思う充と、そのことに罪悪感を感じちゃう私がいるっていうこと、そのこと自体がそもそもそのままでいいのかもしれない。
M:あとは、近い人に自分が知ったことを伝染させていくことかな。不特定多数の人に投げるよりも、身近な誰か一人二人に届いたらいいなっていう姿勢。
S:草の根だね。本当にそれしかないなって思う。今のトイレにポスターを貼るっていう話も、自分が納得して、自分の意思を示すってことだもんね。大事な入り口かも。私たちのこの取り止めのないおしゃべりだって大切だし。
M:それこそ運動をもっとやってる人たちから、「そうじゃなくてこうだよ」って言われたら、「あ、そうか」ってまた思えばいいのかもしれないけど。
S:さっきの勉強量とかコミットしてきた量の話にも戻っていくね。もちろんこうしてほしいって言われたら連帯したいし、バランスが大事なのかな。
まずは自分ができることから
S:今ずっと考えてたんだけど、さっき充が言ってくれた「もっと気軽に身近に考える」みたいなのって、何かに声をあげようって思ったときに結構自分に必要な姿勢だなって。どうしても、全てを網羅してなきゃとか、もっと理解してないと、みたいな気持ちになっちゃう。
今回『ガザとは何か』を読んだあとも、これは二人ともSNSで意思表示をしようってなってそれぞれにテキストを書いたけれど、私は言葉を発するまでにすごく時間がかかった。「何のためにその言葉を発するのか」を考えたとき、本当はもっとスピード感を出すべきだったなって。一方で充は自分の気持ちをさっと素直に言葉にしてたからすごくいいなと思った。
私は何かを言うならば、もっと学ばねば、理解している自分でなければ、みたいについなっちゃってそれが苦しくなったりするから、良い意味で気負いすぎない姿勢を自分も取り入れたい。本屋にいても、本を見ながら、自分がまだ読めてない本とか、学べてないことが頭をよぎってしまうし...。
M:なんか役割分担なのかなって。
もちろん色んなことを語れるようになりたいし、そのために勉強することも大事だけれど、実際に学問として第一線で言葉にしてくれるのは岡真理さんのような専門家の人であって、それを自分がやることは今時点ではできない。だからいい意味でそれは専門家に任せて、どこまでいっても自分がやれることになるのかなって。たとえ岡さんが言っていることが100だとして、自分がそのうちの10しか言えなくても、自分の言葉で理解して、自分の言葉で語る。それが大事なのかなって思う。
S:そうだね。専門家と同じように語ることはできないけど、その一方で「知りたい」って思ったけれど色んな事情でなかなか学んだり読んだりに至らない人と、その情報との間に入ることはできるかもしれない。それしかできないけれど、でもそれってすごく大事なことな気がする。自分の課題として、できるだけ気負わずに、喋ったり、読んだりをしたいなって思う。アフタートークとして記録...。
M:あ、これ続きじゃなくてアフタートークなんだ?(笑)
S:一回締めて、お店も出たからさ(笑)でもさ、これも後々テキストに起こしたいなって思うけれど、きっとまた自分で聞き返したときに「あ、これ間違ってる」とか「これについて言及すべきだったのに私は言わなかった」みたいなことが自分のなかで絶対に起きると思うんだよね。でももうそれもいいじゃんってある程度しないと、無理だなって思う。
M:きりがないね。
S:うん、だからまた何か出てきたら、言ったり書いたりすればいいかなって思うようにしたい。そういう気持ちを、他者にも自分に対してもできる限り持つようにしたい。一定の許しっていうのかな。
今日は三鷹のUNITEという本屋さんで、岡真理さんの『ガザに地下鉄が走る日』を買ったね。手元にも置いておきたいし、人にも貸せたらいいね。何の本を選んでお金を使うかって、それも一つの意思表示だなって思う。
M:そうだし、今回ばかりは純粋に教えてくれてありがとうございます、っていう気持ちで買ったかな。
S:そうだよね。楽しみっていうのは違うかもしれないけれど、読みたかったから買えてよかった。
M:『ガザとは何か』の参考文献にも載っていたやつだね。
S:知人もSNSで紹介してたから読みたかったんだよね。よし、ではありがとうございました。
---------------------------------------------------------
(勝手に!)取り扱い本屋さんリスト
💡随時更新していきます💡
これまでにSNSの入荷情報や店頭で、この本を取り扱ってることを目撃したお店を(勝手に)まとめてみました。実際の在庫情報はお店にお尋ねください。好きなお店に取り扱いをリクエストするのもすごく大事なアクションだと思います。
Twililight(東京・三軒茶屋)
七月堂(東京・豪徳寺)
本屋B&B(東京・下北沢)
エトセトラブックス(東京・新代田)
蟹ブックス(東京・高円寺)
今野書店(東京・西荻窪)
UNITE(東京・三鷹)
道草書店(神奈川・真鶴)
石堂書店(神奈川・妙蓮寺)
MINOUBOOKS(福岡・うきは市)
すでに登録済みの方は こちら